Vol.6「写真家×2020年春」 公文健太郎さん新しい試み

Vol.6「写真家×2020年春」
今だからこそ、新しい一歩を踏み出す。COO PHOTOの雑誌創。
COO PHOTO(クーフォト)プロフィール
写真家公文健太郎が主宰する写真家集団(柳原美咲などが所属)。ルポルタージュ、ポートレート、建築、食関連の撮影
を主に幅広く活動。加えて日本の風土と暮らしを訪ねて「点」を打つのが仕事。
2020年『点』を創刊。『点0号(特集:点)』『点1号(特集:起点)』を発行。季刊発行を予定。
世界中が元気をなくし、加えてコロナ禍によってさらに写真業界が傷ついた今、私たちはどこに向かっていけばいいのか、道標を失ったかのようだった。
そんな迷える時代において、自ら新しい一歩を踏み出したのが、公文健太郎さん。
ネットではなく、あえて紙の雑誌を新たに立ち上げた。そこにはどんな意味と志が込められているのだろう。
古い写真を見返すのも写真を撮ることなんだと気づく

──まずはこの未曾有でもあるコロナ禍のなか、どのようにお過ごしでしたか。
公文 自粛期間の最初の数週間は仕事がキャンセルになったりはしたものの、振り返れば毎日何かやっていましたね。ここ数年はそれこそ毎日どこかへ出かけて写真を撮っていたわけですが、コロナの期間は新しい雑誌をつくることによって、写真と向き合っていたと思います。
写真っていうのは、そもそも過去を切り取ったものじゃないですか。だから古い写真をちゃんと見直すことで、過去を振り返ることができるわけです。そんな写真を見て雑誌に掲載する作品を選びながら、これも“写真を撮る”ということだよね、と改めて感じました。出かけなくても写真やってるじゃん、と。
柳原 自粛が始まったらみんな自宅の中や庭の写真を撮ってアップするようになったじゃないですか。コロナの前だったらそれらは単なる日常の風景だったと思うんですが、今の状況でそれらの写真を見返してみると、以前は感じなかった価値がすごくわかるんです。写真ていうのは置かれている状況や背景によって感じ方がまるで違ってくるんだなって、改めて気づきました。
公文 僕は写真イコール旅でしたから、家の中で写真を撮るのは苦手でした。でも、やってみたら楽しかった。すごい気づきがありましたよ。マニュアルでピントを合わせるのがすごく楽しかったり。今更そんないろんな発見があって、ふと、もしかしたらオレは旅に出ただけで写真を撮った気になっていたのかも、なんて振り返りもあったり。こういう状況だからこそ得られた気づきでしたね。
写真集の流れの中からこぼれた写真を救うために

──コロナ禍の中にあってもご自分で楽しみを発見し、常に前を向かれているのが、公文さんらしいです。とても刺激になります。今回、雑誌『点』を創刊されたのも、そうした新しい一歩でしょうか。
公文 コロナがきっかけというよりは、もともと以前から雑誌はやりたいと思っていたんです。自分で編集した、自分の雑誌を持ちたいと。僕は写真集が好きで、撮影するときも写真集を想定して撮っているし、人の写真集を見るのも好きです。
一方で、フリーランスになってから今までハイペースで仕事を続けてきて、ここらでちょっと仕事の進め方を見直してみたいという思いもありました。ずっと“来るもの拒まず”の姿勢で走り続けてきましたから。そういう思いもあって柳原に「ちょっと雑誌でもやってみようか」なんていうことを具体的に話し始めたのが、今年の1月末頃。コロナの懸念は人々の話題になっていたものの、まさかあの後にこんなことになろうとは予想もしていませんでしたが。
柳原 「ちょっと雑誌でも」という話を聞いて、私は単純に楽しそうだなと思いました。
公文 先日テレビ番組の取材で撮った写真があるんですが、いい写真だけれどちょっとこれはテレビには映せないね、という話になりました。そのとき、だったら、この写真はどうなるの? どこに行くの? という思いがわいてきて、それも一つのきっかけになりましたね。
柳原 雑誌は、世の中に出られなかった“子“たちを救ってあげられるんです。写真集は、どうしてもこぼれる写真が出てくるんです。もちろんその中には写真として素晴らしいのに組みにくい写真も多くて、そういう写真のためにも雑誌とは素晴らしい表現の場所ですから。
公文 キュレーションという言葉がありますが、ストーリーの中で写真を構成していくと、全体のバランスや流れになじまない作品もあります。でも、撮っているときは必ずしもそういうことを考えているわけじゃないですから、全体のストーリーを別にして、“この写真いいなあ!”と言いたい作品も多いんです。そんな“いいなあ!”を、雑誌という形で残したいと思いました。
ストーリーは大事だけれど、そもそも1枚の写真としていいかということも大事にしようというのは、僕の方針でもありますし。


売ることが目的ではなくて、つくること自体が目的
──編集・構成・デザインはグラフィックデザイナーの伊勢功治さんですね。
公文 新しい写真集の仕事で伊勢功治さんと一緒になったとき、雑誌でもやろうかと思っているという話をしたら、「やろうよ!」と言っていただいたんです。
伊勢さんにはずっと長く僕の写真集をお願いしているんですが、僕にない非常に文学的なセンスをお持ちの方なんです。僕は泥臭く被写体と向き合うのに対し、伊勢さんは少し引いたところから紙の上に美しくまとめ上げてくれる。そんな伊勢さんが「やろうよ!」と言ってくれたことで、一気に加速しました。
その日の夜、さっそくタイトルの話をしました。僕の写真集って、いつも僕が提案したタイトルはボツになり、伊勢さんの案が採用になるんです。だから伊勢さんは僕の写真集の名付け親でもあるわけです。ところがこの雑誌に関しては、僕が『点』にしたいっていったら、初めて伊勢さんがOKを出してくれました。
──『点』にはどんな気持ちが込められているのでしょう。
公文 柳原と僕は旅をして写真を撮っていますが、その目線はやっぱりお互いに違うんです。2人で歩けば1人よりも距離が伸びるし、目線が違うから、点もたくさん打てる。そんなふうにして日本中にたくさん点を打ってつないでいこうという気持ちをタイトルに込めました。
そうして撮った写真に伊勢さんや、山伏であり作家である坂本大三郎さんに文章を添えていただきました。この文章が、僕らにとっては一番のご褒美ですね。
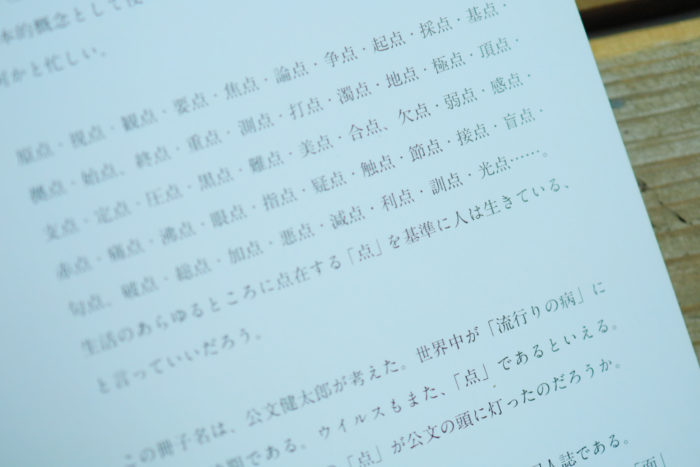
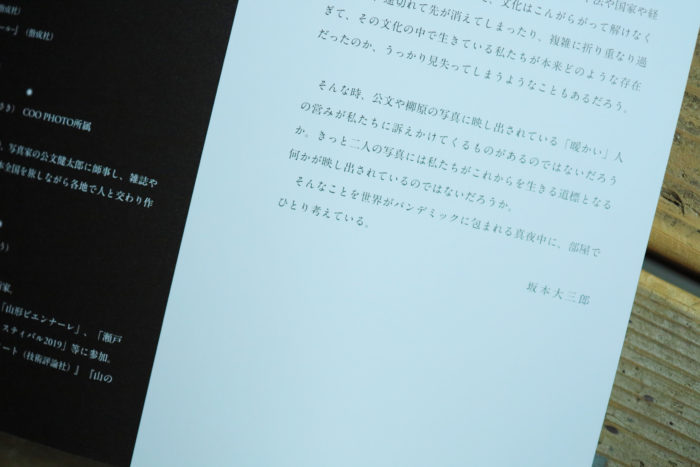
──印刷や販売についてはいかがでしたか。
公文 最初はネット印刷でつくっちゃおうかと思っていたんです。手探りでのスタートでしたからね。でも、伊勢さんが力を貸してくれることになって、それならネットじゃなくてちゃんと印刷しなきゃという思いから、光村印刷さんにお願いしました。
部数は200部で、定価1200円。私のギャラリーとか仲間の店などに置いてもらいたいなと思っています。売るっていうより、たまたま手に取った人が「欲しい」といってくれたらお分けする、というスタンスですね。僕らの写真を知らない人がページを開いてくれたら、本当に嬉しいです。
もっと本音を言えば、一部も売れなくてもいいとさえ思っています。売れることが目標ではなくてつくること自体がモチベーションの源泉ですから、つくり続けていくためにも、売れるかどうかは気にしていません。だから、たとえ一部も売れなくたって、休刊はしない。
実際に買ってくれているのは、一度会ったきりでFacebookづけでつながっている人だったり、昔は付き合いがあって今は少し離れている人だったり、いろいろですね。最初に「買いたい」と連絡をくれたのは昔お世話になった編集長だったけれど、これはすごく嬉しかったなあ。
紙媒体ならではのスピード感が自分のスタイルにフィットする
──ネットの時代に、紙の雑誌を立ち上げるということについては、いかがですか。
公文 ネットより簡単でしたよ。
──えっ、そうなんですか?
公文 ネットの場合、目的が見えにくい気がするんですよね。例えばアクセス数を確認したり、サイトの中をどう見てもらうか動線を考えたり、売り方を構築したりしなければなりませんよね。その点、紙媒体はすごくシンプル。できることが少ないっていうか。写真を選んで、編集して、言葉を付けてもらうっていう、すごくシンプルな流れです。やっぱり僕はそんな紙媒体が好きなんですよ。
柳原 ネットはいつでも見られるけど、その分、流動的で散漫ですよね。紙だと自分の手元に置いて、10分なら10分、その世界に浸れる。そういうところが紙媒体の魅力じゃないでしょうか。
公文 僕は今まで農業や半島というキーワードを持って歩きながら目にとまったものを撮り、写真集にしてきたけれど、自分の撮っていくスタイルと紙媒体のスピード感というのがすごく合うんですよね。
それに紙だと、前の写真が残っちゃうじゃないですか。昔つくった写真集って今見ると恥ずかしいけれど、だからといってネットのようにサクッと削除できるわけじゃない。そこが怖さでもあり、紙ならではの良さでもあると思います。
──公文健太郎の写真を見るなら、紙が一番公文健太郎らしく見える、と?
公文 いや、そこは限定するつもりはないのです。いまは4人で事務所をやっているから、4人の視点があれば何でもできちゃうじゃないですか。例えばですが、いきなりスポーツ写真を撮るとか。やりたいと思ったことを、紙に残すという責任のもとで自由にやっていきたいと、それだけですね。ただ、紙が一番合うというだけです。
この雑誌がきっかけで新しい仕事につながったら、という思いというか“下心”もありますよ笑 これまでもクライアントさんといい仕事をさせていただき、それが膨らんで作品となってきたというものがあります。今後もそれは変わりません。仕事で地方に足を運ぶと、ちいさな旅館とか村とか、たくさん目にするわけです。先日もある旅館の女将さんの写真を仕事で撮ったんですが、それで一冊雑誌をつくって、たとえば海外へ持って行けば、いろんな反応が得られるでしょ
う。そんな反響からまた新しい仕事につなげていきたいと。そういうことも含めて、この自粛の期間に雑誌を立ち上げたのは、自分の表現を見直していく節目を迎えたという思いがしています。

個人で動けるからこそ新しい価値を生み出せる
──業界全体が逆風の中でも新しい楽しみを創造しながら一歩を踏み出しているところに、公文さんってクリエイターだなあと感じます。
公文 今はクライアントも厳しいし、世の中の企業は本当に大変な思いをしているでしょう。その中で僕らの場合は個人で動けるし、そこから新しい価値を生み出せるんです。すごく幸せなことだと思います。
柳原 写真家っていうのは、テーマを探すところからアウトプットまで自分でできてしまうという点でも、得な職業かもしれませんよね。
公文 クリエイターというより、自分の中になにかあるタイプではないのです。ひとまず動いて答えを見つけていくのが僕たちのススメ方なのだと思います。

──公文さん、柳原さんがそういうお考えで実際に動いていらっしゃるというのは、写真業界のみならず、社会にとっての大きな希望になると思います。0号が「点」で1号が「起点」ときて、次号は何の点になるのでしょう。
公文 何にしましょうかね。考えないと。0号は、ふわっとした点のイメージなんです。そして1号は、地球とか、土とか、自然とか、そういうものをどこかにイメージしながら、芯のある写真を中心につくりました。
2号はこれからですが、今は撮影しにもいけませんし、今まで撮った写真をなんども振り返りながら構成したいですね。いいものにしていきたいですし、止まらずにずっと続けていくつもりです。
──これからも楽しみにしています。今日はありがとうございました。
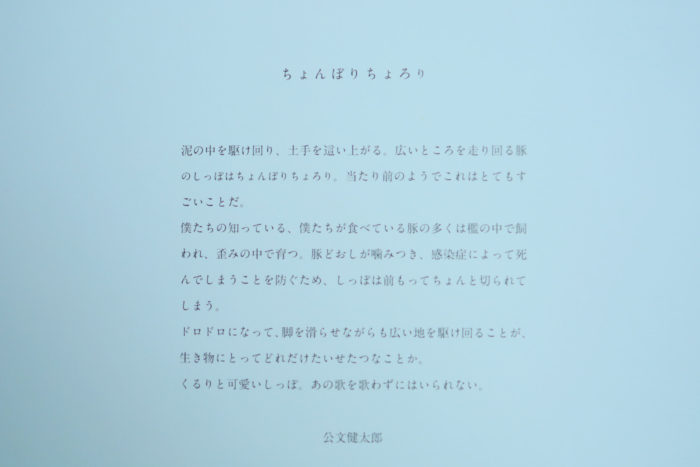

※このインタビューは2020年6月9日、MYD GALLERY(港区南麻布)で行いました。
公文健太郎(公文健太郎)さん
1981年生まれ。雑誌、書籍、広告でカメラマンとして活動しながら、国内外で作品を制作中。2012年、日本写真協会新人賞受賞。写真集に『大地の花』(東方出版)、『BANEPA』(青弓社)、『耕す人』(平凡社)、『地が紡ぐ』(冬青社)、フォトエッセイに『ゴマの洋品店』(偕成社)、写真絵本に『だいすきなもの』『世界のともだち』(いずれも偕成社)などがある。
柳原美咲(やなぎはら・みさき)さん
1991年群馬県生まれ。2015年日本写真芸術専門学校を卒業後、公文健太郎に師事する。雑誌や広告でカメラマンとして活動する一方で、日本全国の温泉地をめぐり”湯のある国”の文化を取材。ちなみに体を洗うのはボディソープではなく石鹸派。
あとがき
写真と暮らし研究所 鈴木さや香
写真を撮る人には特に、チャンスでもありピンチでもあったのがこのコロナウィルスと向き合う自粛期間であり、自由に撮れないというもどかしい思いの日々だったのではないかと思うのです。
写真が生きがい、写真=生きること と言い切る人も多いこと思います。しかし、思うように写真が撮れない日々が訪れてしまった。
けれども、よくよく考えればその原因が今回は見えないウィルスだっただけで、不自由とはいつ自分が置かれるか分からないものです。病気や、怪我、妊娠出産、介護、長い人生の中で一度や二度の不自由は必ずやってきます。
そんなときに、写真が撮れない自分とどう向き合うのかはプロだけではなく、趣味を大切にしている写真愛好家にも重要なポイントです。嘆いていくのか、自分ができることを少しずつやっていくのか、沢山の人が同じ状況下で考えることでしょう。
今回のコロナでは精力的に活動している写真家やフォトグラファーほど、すべての停止は大きな事件のようでした。けれども、そんな中でなんだか一際前向きな試みをしているように見えたのが公文健太郎さん率いるCOO PHOTOの雑誌創刊でした。カメラ誌が続けて休刊となり、写真を愛するあまり、焦りや空虚な時間を過ごした人も多かったでしょう。けれども公文さんの歩みは躊躇することを知らないようでした。
「自分たちの写真を救うために。」
その想いは誰かに委ねることなく、自分たちで形にしていくから意味があると、衝動のような、けれども力強い一歩を踏み出されました。
誰かからの承認を獲る、または注目されたりお金を稼ぐなどのことにより満足すれば、その時の自分が対峙した唯一無二の時間が満たされた気になってしまうのは仕方ないのかも知れません。
けれども時間が積み重なっていけば、写真データはどこかに存在しても、記憶の出入り口は閉まったまま遠くに消えてしまうでしょう。いったい自分としてはどうだったのか考えることは、写真を撮るのと同じくらい重要なことかもしれません。
公文さんからは、誰かに向けることよりも、まず自分が納得するために、ただそのために繰り返すことが、いずれ歩みとなるというメッセージをいただいた気がしました。それはとてもシンプルで清らかな営みだと。ただ自分が納得するという、それが一番大変なので誰かに承認を任せたくなる人も多いのかも知れないと思います。
そして、それらは行動を共にする柳原さんにも溢れて伝わっていく。柳原さんの中にある感性も刺激され溢れでて、公文さんに伝わっていくのでしょう。力強いやさしい写真とは、美しい写真とは、自分や自分の向き合った時間を大切にすることで仲間や周りの人たちをも安らかにし、結びつき、生まれくるものだとお二人を見て思いました。
お二人で今までの時間を見返しながら、自分たちの写真ために作った雑誌「点」。それは明るく輝いて浮かぶ星のようにも見えるのでした。02号を楽しみにしております。
Text:丹後雅彦
インタビュー/写真:鈴木さや香





